印紙税(いんしぜい)
契約書に貼る収入印紙の税金です。契約金額によって印紙税額が決まります。印紙税額についてはコチラを参照して下さい。
ところで、契約書や領収書などには収入印紙を貼るものという認識は浸透していると思いますが、何故貼るのか?収入印紙を貼る意味を考えたことが有る人は少ないのではないでしょうか。
収入印紙は切手のような大きさと素材で、最も金額が低いもので1円から最高額のものは10万円まで全部で31種類有ります。
収入印紙を貼らなければならない書類の事を「課税文書」といいます。
課税文書はいくつかの種類があり、国税庁が公表している「印紙税額一覧表」に1号から20号までの各書類の詳細と印紙税額、主な非課税文書が記載されています。印紙税額一覧表はコチラからダウンロードできます。
収入印紙を貼ることによって課税文書作成の際に定められた税額を納税をしたこととなります。
注意すべき点は、収入印紙は貼っただけでは納税したことにはならないという事です。
貼った収入印紙に割印(わりいん)ををする必要があります。印鑑の代わりに署名でもOKです。
一般的には割印と言っておりますが、印紙税法での正式名称は消印(けしいん)と言います。
目的は、印紙の再利用防止です。
再利用ができない状態であれば印鑑押印しなくても有効です。(署名でもOK)
割印(消印)を押すことは法律で決められています。
収入印紙を貼り付けていても割印(消印)がされていないと納税したと認められず、過怠税が追加で課せられることがあります。過怠税は本来納めるべきだった収入印紙の額の3倍です。

印紙の割印を押し忘れただけで本来の額の3倍のペナルティが課せられるんですね。
気を付けましょうね。
売買契約書などでは収入印紙の割印を売主と買主の当事者全員が押印するのが慣例となっておりますが、印紙税法では全員の押印が無くても有効です。
したがって、収入印紙に売主の消印(押印)はされているが買主の押印(消印)を忘れてしまった場合などは
わざわざ、押印(割印)をするために当事者が集まらなくても問題は有りません。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)
登記を行う際にかかる税金です。不動産の価格や地目、登記の内容によって税額が違います。
登録免許税についてはコチラを参照下さい。
不動産購入に関係する登記は主なものとして「所有権移転登記」と「抵当権設定登記」です。このうち、「所有権移転登記」は自分でもできますが、「抵当権設定登記」も同時に行う必要が有る場合は司法書士へ登記を委任する事となります。
抵当権者(金融機関等)の承諾が有れば自分で登記を行う事ができますが、大抵の金融機関は承諾はしないです。
司法書士へ登記を委任した場合は登録免許税に加え、司法書士報酬が必要となります。司法書士報酬額は各司法書士によって任意に決めていますので登記を委任する前に確認をするようにして下さい。
尚、登録免許税には軽減措置が有ります。詳細はコチラの法務局のウェブサイトを参照して下さい。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことです。
購入物件に入居してしばらく(2~3カ月)すると、自治体から納税通知書が送られて来ます。
この税金は地方税で、納税先は物件所在地の都道府県です。具体的には都道府県の税事務所で納税の手続きをします。
不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算されます。
課税標準額とは法律上、その不動産の価格のことです。実際に売買したときの時価ではなく、原則として固定資産税評価額(以下、評価額)と呼ばれる公的な価格が使われます。
この評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。
税率は原則4%と定められていますが、この税金には軽減措置があります。詳細は総務部財政局税務課直税係のウェブサイトを参照して下さい。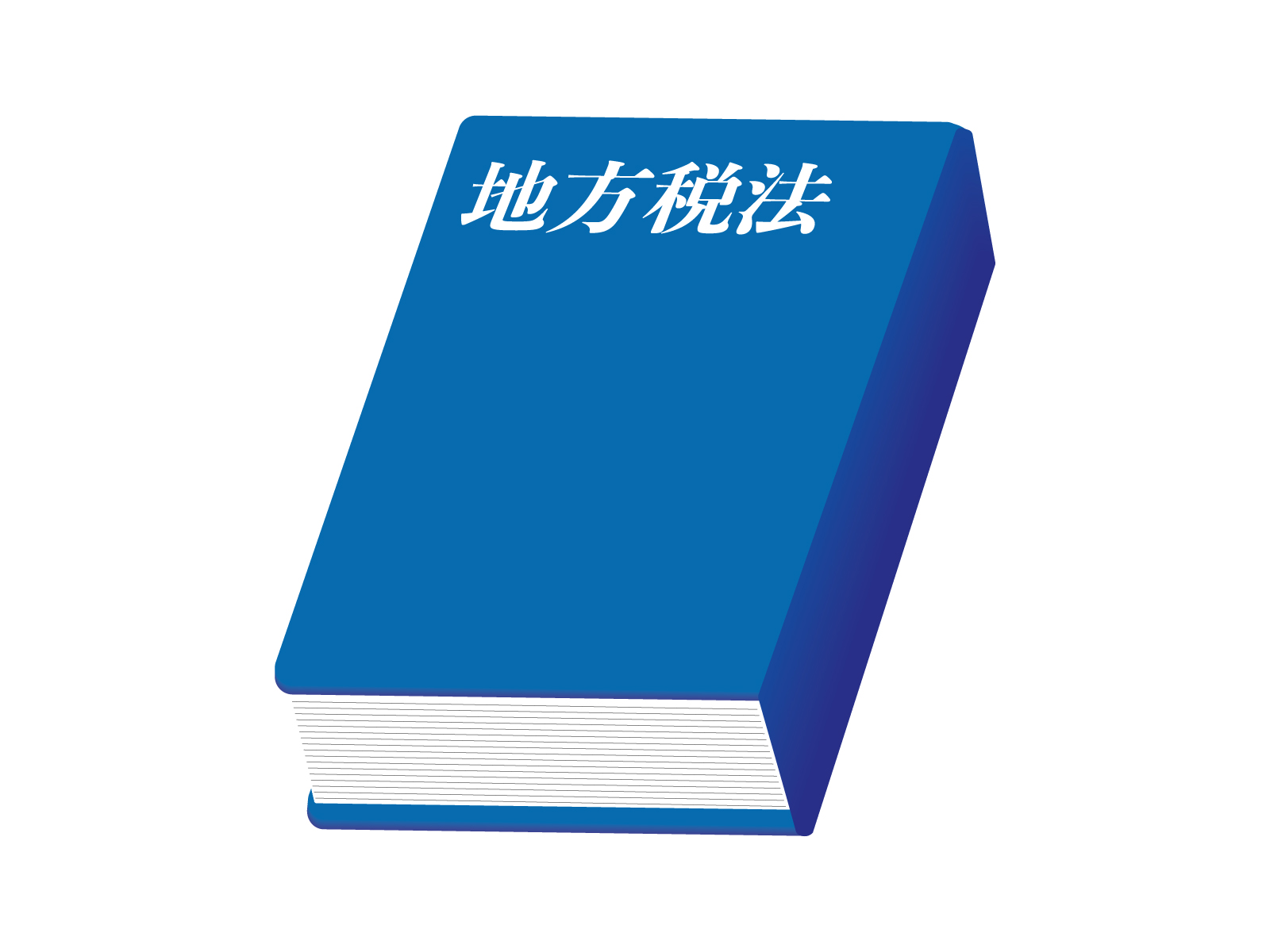
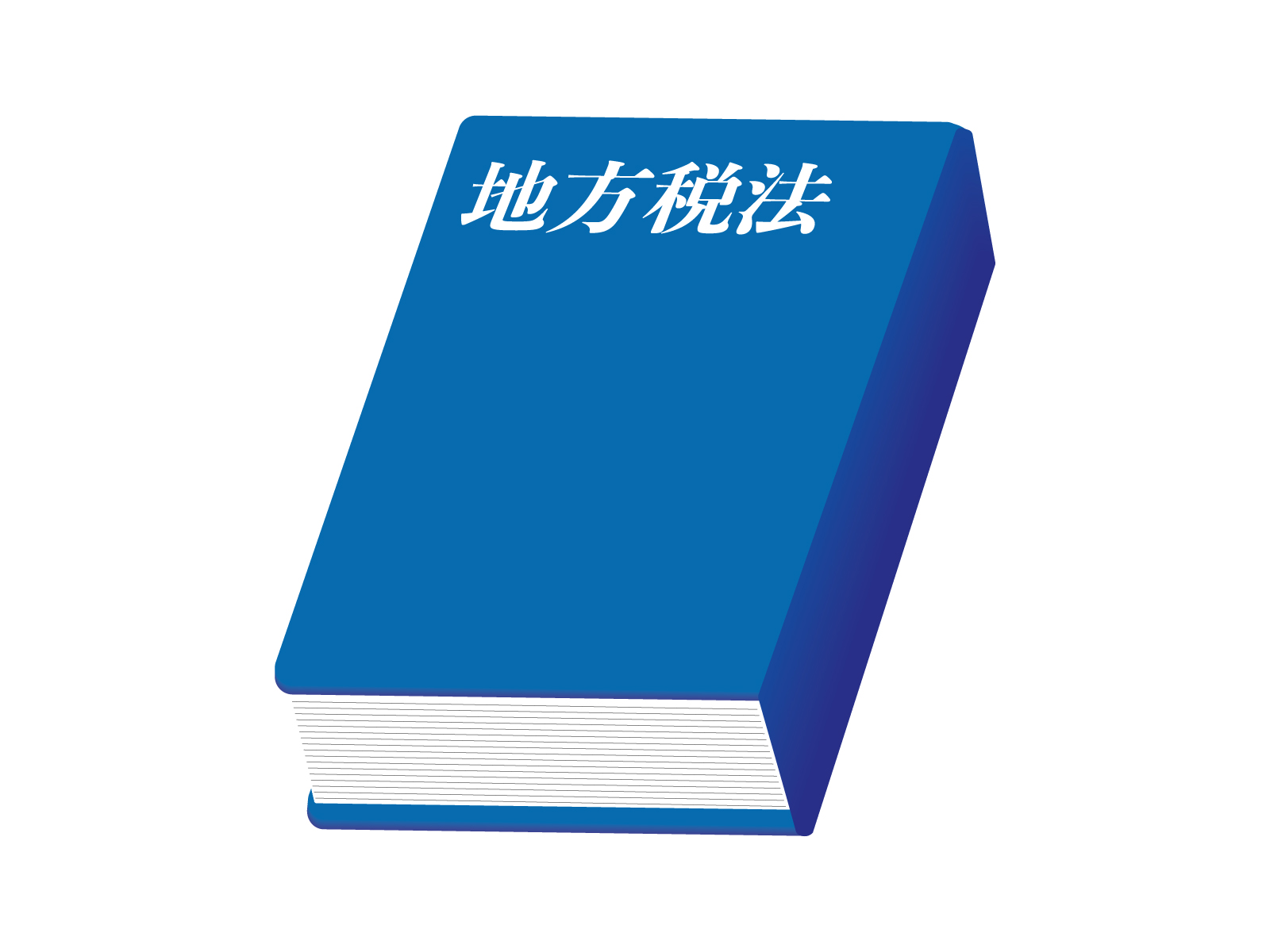



不動産取得税の軽減が受けられる場合は
かなりの額が節税できるので、
要チェックですよ~。
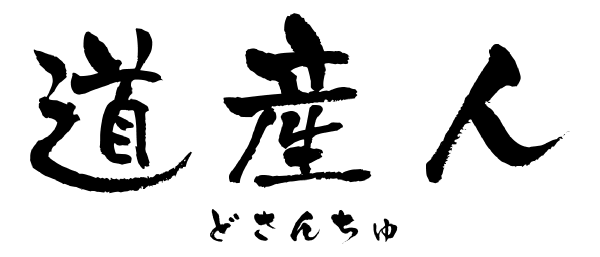

コメント